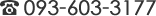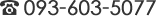こんにちは。NAVONAの上田です♪♪
お久しぶりです。皆様お元気ですか(>u<)??
正月も終わり落ち着いてきた頃ではないでしょうか。。。?
NAVONAも怒涛の成人式が終りようやく落ち着いてまいりました(;^_^A
落ち着いたところで久しぶりに豆知識コーナーでもどうでしょうか、、、!?
今回は、もうすぐ2月節分の時季ということで【豆まきと恵方巻】について書いていこうと思います( ´艸`)
そもそも節分って何の日?
そもそも節分とは文字通り「季節を分ける」日だそうです。
立春の前日、お正月に対する大みそかのようなものらしく、本来は立春だけでなく立夏・立秋・立冬の前の日も節分ですが、現在では立春の前の日だけが行事として残っているようです。
明治6年に太陽暦が採用されるまで使われていた太陰太陽暦(太陰暦、旧暦)!!新月から次の新月までを1か月として12か月を1年と数えます。ただ数年すると季節と月がずれが、、、そのずれかたが1か月分に近くなると3月の次に閏月(閏3月)を入れて調整します。とにかくややこしくなりますね(;^_^A 江戸時代以降 旧暦の新年と重なる立春(2月4日頃)を節分として重要視されるようになりました。
2020年までは2月3日が節分でしたが、2021年は2月2日でした。
2021年~2057年まで、4で割り切れる年は3日。4で割って1余る年は2日が節分らしいです。
節分の目的は?
節分といえば、「鬼は外。福は内。」の掛け声で鬼を追い払う豆まき。
豆まきは、室町時代の看聞日記に「抑鬼大豆打事、近年重有朝臣無何打之」とあることからすでに宮中や都の公家の内では豆まきが行われていた記録もあり古くから行われてきた儀式といわれています。
元来中国から伝わったとされ「追儺(ついな)」「鬼払い」のという災いを祓う儀式がもとになっています。
豆・穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっているとされていたこともあり、「魔目(豆・まめ)」を鬼の目にぶつけることで鬼を滅し邪気(鬼)を払い無病息災を願うとされてきました。
魔(鬼)を滅する「魔滅」からマメになったそうです。
最近では神社仏閣で芸能人が豆をまく姿は、節分の風物詩です。地元出身の有名人やその時々の人気者が招くところが多いですよね。
因みに千葉県の成田山新勝寺の豆まきは、恒例として当代の歌舞伎俳優の市川團十郎が行うそうです。これは初代市川團十郎が帰依していたお寺という縁がもとになっています。
江戸時代、團十郎の「にらみ」という芸は“魔を払う”と神格化されており、「團十郎(がセリフをしゃべるとき)のつばきがかかると風邪をひかない」とも言われたほど。そうした團十郎の“ご利益”もあって、成田山新勝寺では当代の市川團十郎が行っているようです。
【豆ならなんでもいい、、、!?】
ほとんどの地域では「大豆」を使いますが、北海道・東北・北陸などのおおよそ8割と、鹿児島や宮崎の一部はピーナッツ(落花生)をまくそうです。
大豆は五穀(米・豆・麦・粟・ひえ)で農耕民族である日本人には欠かすことのできない食べ物です。
豆をまくところが多数ですが昔は米・麦・粟・炭なども使われました。
米・豆は神聖なものとされ特に豆は粒が一番大きく悪霊を追い祓うには最適とされたからです。
ピーナッツ(落花生)をまくのは粒が大きく拾いやすく皮がついていて地面に落ちても汚れないのが理由のようです。
その中でもよくつかわれるのが【福豆】。福豆は炒ったものですが、何故 生を使わず炒ったものを使うのかというと拾い忘れた豆から芽がでてしまうと縁起が悪いとのこと!!なので、撒く際には炒った豆をおすすめします。
【恵方巻について】
「恵方巻」について話す前に「恵方詣り(えほうまいり)」という言葉は知っていますか?
古来の正月行事の一つ。恵方参りとも書くそうです。

1月1日(元日)にその年の恵方にある社寺に参拝してその年の幸福を祈願する恵方とは歳徳神が在位する方角で、十干に従って毎年変わる。今日ではあまり見られない慣習である。
居住地から見て恵方に当たる社寺に参詣するのが、江戸時代までの恵方詣りの形であった。
明治以後、都市周辺に鉄道網が発達すると、恵方詣りの対象も郊外・遠方の有名社寺に広がるようになった。競合する鉄道会社間(国鉄を含む)では元日の参詣客を誘引するために宣伝合戦とサービス競争が行われた。文明の開化の結果ですね!!
【恵方巻の具について】
太巻きには7種類の具材を使うとされ、その数は商売繁盛や無病息災を願って七福神に因んだもので、福を巻き込むと意味付けされています。別の解釈もあり、太巻きを逃げた鬼が忘れていった金棒(鬼の金棒)に見立てて、鬼退治と捉える説もある。
因みに代表的な具材は
また、大正時代から昭和時代初期には漬物が度々挙げられた。他にも焼き紅鮭、かまぼこ(カニ風味かまぼこ)、高野豆腐、しそ(大葉)、三つ葉(ほうれん草)、しょうが、菜の花、ニンジンなどが使われることも、、、。
2000年代以降ではサーモン、イクラ、イカ、エビ、まぐろ(ネギトロ・漬けマグロ)などを使い「海鮮恵方巻」と称して店頭で売られることもふえましたね。具材の種類数でも7種にこだわらず、2種や5種などと少なくしたり、11種・12種・15種など多くする場合もあるようです。
【恵方巻の発祥、、、!?】
恵方巻の起源・発祥は諸説存在しどれも信憑性は定かではなく複数の説があるようで、調べると多くありすぎてかけなかったので、気になる方は「恵方巻とは」で調べてみて下さい(>u<)♪♪
恵方は毎年変わり、その年の十干(じっかん)によって決められますが、方角は、東北東・西南西・南南東・北北西の4方向しかありません。 十干で甲・己の年は東北東、乙・庚の年は西南西、丙・辛・戊・癸の年は南南東、丁・壬の年は北北西の方角となっています。
いろんな思いを込めながら食べるのもいいですね。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。