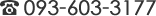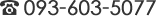あけましておめでとうございます(⋈◍>◡<◍)。✧♡
NAVONAの上田です♪♪
新しい年も明け、怒涛の成人式も終わってようやく落ちついた営業が戻ってまいりました(>v<)
忙しい日々も過ぎたので、久しぶりに【どうでも良い豆知識】を更新したいと思います!!
今回はちょっと先のはなしになりますが、
2月11日の【建国記念】について書いていこうと思います(^w^)
興味のない方はそっとページを閉じてください(・v・)WW
2/11は何の日!?と聞かれて「建国記念日」と答える人が多いと思いますが、正しくは「建国記念の日」というそうです。私も「そんなのどっちでもよくない。」と思ったのですが、調べてみると長い歴史が関係しているようです。
「建国記念の日」は国民の祝日に入ります。
この2月11日という日付は、初代天皇とされる神武天皇の即位日である【旧暦】紀元前660年1月1日にあたり、明治に入って【新暦】に換算した日付というわけなのです。
| ※神武天皇(じんむてんのう)は日本神話に連なる伝説上の人物。 |
神武天皇が即位した日を日本の建国された日として祝うことを(紀元節〔きげんせつ〕)と呼んでいました。
戦後占領軍の意向で【紀元節】は祝日ではなくなりました。
なぜ戦後なくさなければならなかたのか・・・?それは、「紀元節を認めることにより、天皇を中心とする日本人の団結力が高まり、再び米国の脅威となるのではないか」というGHQの意向で、紀元節は廃止されたそうです。
しかしその後、紀元節を復活させようという動きが高まり、反対する動きを抑え建国を記念するための祝日を設けることとなりました。
因みに、当時のテレビ局が行ったアンケート調査により、全国民の80%以上の人が「建国を記念する日」を望んでいるということがわかりました。その結果、1966年になり建国記念の日に関する提案が承認され、翌年1967年から適用されることとなりました。建国記念の日が成立するまでには「日本の正確な起源などわかっていないのに建国記念など定められない」など専門家による多くの議論があったようです。
結論「記念日」ではなく、「記念“の”日」とするワケとは
②現在の歴史学では神武天皇の存在に確証がなく「正確な起源が分かっていないのに建国記念日など定められない」とする学者からの意見が多くあったことがあげられます。最終的に、史実に基づく建国された日とは関係なく、たんに建国されたという事実をお祝いするという考えのもと、「記念日」ではなく「記念の日」となたそうです。